多くのひとがそうであろうように例に漏れず『火垂るの墓』が苦手だった。
苦手、見ず嫌いと言ってもいいかもしれない。
子供の頃から「戦争」以前に「悲しい話」が苦手というか、悲しくなるから見たくないというか。『火垂るの墓』もそうだし『デジモンアドベンチャー02』の『サヨナラ、賢ちゃん……』の回も『ポケットモンスター』の『ピカチュウのもり』も苦手だった。
死や別れといったものに対する恐怖心というか、漠然とした悲しさを感じすぎてしまう。というとナイーブかもしれないが、そういう子供だったような気がする。
そのような印象をずっと抱いてきたので『火垂るの墓』をあまりしっかり見たことがなかった。「戦争を扱ったアニメーション映画で主人公の兄妹が死んでしまう。」という漠然とした認識しかしておらず、その認識をしているということは何らかの形で部分的にでも見たことはあると思うのだが、そのまま30も半ばになりつつあった。
また、今年が終戦80年であることとは別に1,2年ほど前から、第二次世界大戦における日本の戦争被害と加害に興味を持ち始めていた。それともまた別件で静岡市美術館で開催されていた『高畑勲展-日本のアニメーションに遺したもの』にも行っていた。
今年の夏には金曜ロードショーで放送されるとほぼ同時にNetflixでも配信が始まり、見るハードルは下がり、自分自身見る準備もできていた。
そして録画した金曜ロードショー放送のものを見た。
これは順序としていいのか悪いのかはわからないのだが、先にNHKで放送されていた『ETV特集 火垂るの墓と高畑勲と7冊のノート』を見ていたことで補助線がビンビンに引かれたこともあり、思いの外感情を持っていかれるようなこともなく、見られてしまった。
自分が30年以上生きてきた中で見聞きしてきたことによって、ある程度“わかって”いるのもあり、物語もそれはそうとしてアニメーション映画としてめちゃくちゃすごいな。と、当たり前のことを思って見てしまったのだった。
本でいうと『鉄の暴風:沖縄戦記』、あとは今年の夏は再放送も含めてたくさん放送されていたNHKのドキュメンタリーなんかを見ていると、これは比較として正しくはないと思うが、『火垂るの墓』で語られるようなことは特筆すべき悲劇とかではないことがよくわかる。あのようなことは“よくあること”であり、戦争というのはあのように子供が衰弱して死んでいくのだ。それはもちろん正しいことではない。それを前提としてそういうことが起こるのが戦争なのだ。ということを、ああ、そういうことだな。と納得感を持って見た。
戦争を描いたアニメーション映画は数多くあると思うが、強いて言えば『火垂るの墓』は5歳の女の子・節子が徐々に衰弱していく姿。を淡々と見せていく表現はアニメーション映画ならではのしんどさがつきまとった。
それは、自分が2人兄妹の兄というのもあり、どうしても清太に寄り添って見てしまう側面はあったかと思う。
30過ぎの自分は清太に対し、もっとどうにか上手く大人に頼ってくれ。と思うのだが、14の自分は清太ほど妹の面倒を見て優しくすることはできていなかった。14歳の清太のいっぱいいっぱいな部分を思うと、何が正解なのかは全くわからない。
当たり前だ。清太は馬鹿だが14歳で子供だ。
近年は西宮のおばさんを否定しない意見が散見され、見たことがなかったのでなんとも言えなかったのだが、見てわかった。
あれを肯定することはできない。
と、同時に、あのような状況で西宮のおばさんのようにならない自信がどこにもない。
なりたくはないが、なってしまうかもしれない。西宮のおばさん擁護論の側に少しだけ立つとしたら、「自分があのような状況で西宮のおばさんのようにならない保証がどこにもないから否定しない」はあるのかもしれない。と少しだけ思ったが、じゃあ14歳と5歳の兄妹を追い出すことが間違っていないわけがないので、やはり肯定はしたくない。
清太は少しは仕事ができるかもしれないが、節子を誰が面倒見るのか。という話になったら西宮のおばさんはやってくれないのではないだろうか。
結局清太は節子の面倒を見るしかないし、それが清太がやるべきことであった。それと同時に、もう少し上手く立ち回れれば……とは思うが、清太は14歳だ。だが、清太が馬鹿だからという理由で節子を死なせてしまうのも、清太自身が死んでしまうのも自己責任で清太が悪い。などとは全く思いたくない。
戦争がなければ死なずに済んだのは明白だ。
そして戦争というのはあのような立場の弱い者から死んでいく。
あらためて書くが『火垂るの墓』という物語は、あの戦争の中であった特筆すべき悲劇ではない。あのような悲劇が数えきれないほどあったのが、あの戦争なのだ。
それは『火垂るの墓』の物語を矮小化したいわけではない。
清太の死を発見した駅員の「またか。」といった反応とその後の淡々と業務をこなす様子に“あの程度のこと”が日常茶飯事だったことが伺えることの“異常さ”についてもっと考えなければいけないのではないか。
2人が死んだのが「戦後」であることは今回見るまで知らなかった。
当たり前のことだが、戦争が終わったからといって全てが終わったわけではない。
戦争が終わっても戦争の影響で死ぬひとがいること。
お国のため。という言葉の空虚さについても考える。
なぜ清太と節子は死ななければいけなかったのか。
録画した金曜ロードショーのエンドロールを途中で切ることができなかった。
それくらいにはくらった。
「核兵器はコスパがいい。」などと言う政治家が出てきてしまった2025年の日本で高畑勲監督の「(『火垂るの墓』のような映画が)これからの戦争を防ぐ力にはならないと思うのです。」という言葉を噛み締める。

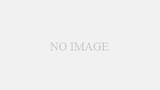
コメント